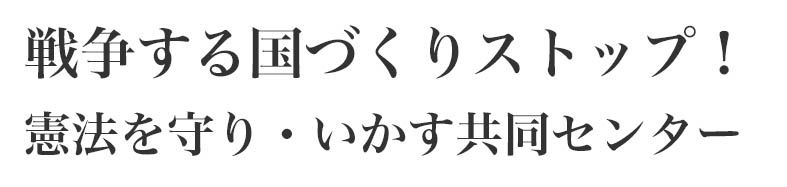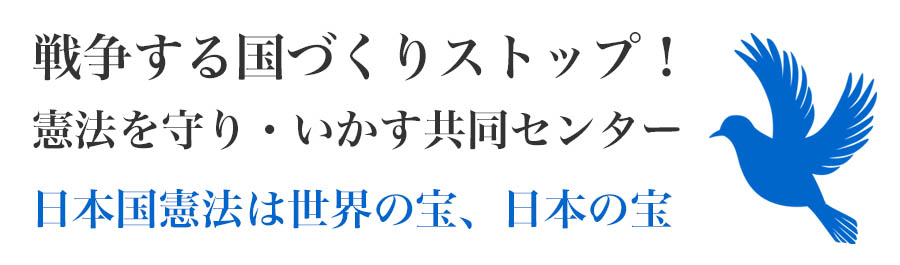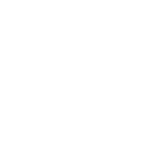一橋大学大学院教授 渡辺 治
はじめに 安倍政権挫折による改憲の新局面
2007年7月の参院選で安倍自民党が大敗し、安倍政権が倒壊して、明文改憲をめぐる状況は激変した。自民党政権による明文改憲強行の危機、憲法にとって間違いなく戦後最大の危機はひとまず回避された。
しかし、改憲を求める内外の圧力は依然として安倍の後を襲った福田政権を圧迫している。そのため、福田政権は、安倍政権の敗北の教訓を踏まえて、破綻した改憲路線を建て直すための新戦略の構築を迫られている。その焦点が海外派兵恒久法である。
そこで本稿では、いったい福田政権の改憲新戦略とはいかなるものか、またなぜ海外派兵恒久法がその焦点になっているのかについて検討し、今後の改憲阻止のとりくみを展望したい。しかしこれらの問いに答えるには、そもそも、安倍政権による改憲強行路線はなぜ挫折を余儀なくされたのかの検討からはじめなければならない。その理由が、改憲をめぐる現在の状況をつくりだしているだけでなく、福田政権の改憲戦略の手も縛っているからである。
1 安倍政権による改憲強行路線はなぜ挫折したのか?
(1)安倍政権は改憲をどこまで進めたか
任期中の改憲実行を最大の課題に掲げて登場した安倍政権は、以下のような戦略を立てた。
改憲実行には、憲法96条が定める2つのハードルを越えることが必要であった。ひとつは衆参両院の3分の2の多数を獲得して、改憲案を国会で発議すること、もうひとつが、その改憲案を国民投票にかけて過半数の賛成をうることである。安倍政権はこの2つのハードルを越えるために必要な手だてをまず完成させ、2期6年でこの2つのハードルを越えようとはかったのである。私は、これを「改憲実行のためのクルマの両輪戦略」と呼んだが、そのひとつは、衆参両院議員の3分の2の多数を獲得できるような改憲草案づくりであり、もう一つが改憲案の国会での審議や国民投票手続を定める改憲手続法(いわゆる国民投票法)の制定である。
実はこのいずれの課題もすでに安倍政権の前の小泉政権時代から進んでいた。第1のハードルを越えるための改憲案づくりでは、すでに2005年10月に自民党新憲法草案が党内タカ派の反発を抑えて完成されていた。だから、安倍政権としては、民主党が改憲草案を作成するのを待って改憲案づくりの協議に入ればよかった。
第2のハードルを越えるための改憲手続法についても、すでに小泉政権末期から与党と民主党の協議は進んでいた。しかも改憲手続法の中には、改憲案を審議し、国会にかけるための憲法審査会の設置が謳われていたから、この改憲手続法を制定することによって、第1ハードルを越える作業も進展することになっていた。そこで安倍政権は、就任早々、改憲手続法制定に向け、大車輪の活動に入ったのである。自、公与党は、民主党を抱き込むために、民主党の修正案に「大胆な」譲歩を繰り返した。2006年末にかけて、衆院の憲法調査特別委員会を舞台に、自、公与党と民主党との協議は進行し、年末には両党の共同修正案を出す寸前まで協議は進展した。
ところが、2007年年初から自、公与党と民主党の蜜月状態は一転険悪な雰囲気に変わった。年頭記者会見で安倍首相が、「今通常国会での法案成立を期す、民主党が反対するなら単独でも通す」と宣言したことに端を発していた。安倍首相のこうした強硬発言の背後には、民主党を率いる小沢代表が、参院選をにらんで徹底対決路線をとり、改憲手続法に関しても現場の協調ムードとは裏腹に、「民主党案を丸のみしなければ賛成しない」と強硬姿勢をとっていたことがあった。安倍首相としては民主党につきあって2007年通常国会で採決できないような事態になれば、改憲手続法の施行を3年後とした手前、手続法の施行は2011年以降となってしまい、「任期中の改憲」実行はおぼつかなくなるという危惧があった。逆にたとえ、ここで強行しても、07年夏の参院選で自民党が勝てば、小沢は退陣を余儀なくされ、民主党との協調は再開されるだろうという見通しもあった。こうして、安倍政権は、改憲手続法の強行に踏み切ったのである。
2007年5月14日改憲手続法は可決成立した。一応、安倍政権はクルマの両輪を作った。あとは、参院選を乗り切って、民主党を巻き込みながら、改憲案づくりに入るのみであった。
(2)改憲強行路線挫折の要因
ところが、07参院選で安倍自民党は歴史的大敗を喫した。「安倍やめろ」コールを振りきって改造した安倍政権は結局9月12日に退陣を余儀なくされた。6年どころか1年足らずの退陣であった。安倍政権の倒壊とともに、改憲強行路線は大きな挫折を余儀なくされた。
九条の会運動が世論を変えた
改憲強行路線を挫折に追い込んだ第1の要因が改憲反対運動の盛り上がりにあることは明らかである。改憲反対運動が世論を変えたのである。
その中でもとくに注目されるのが、「九条の会」の運動である。改憲が政治日程にのぼり、自民党内で改憲草案づくりが始まった2004年6月、改憲に危機感を持った加藤周一氏ら9人の呼びかけで、「九条の会」はスタートした。九条の会が全国に九条の会の結成を呼びかけて以来、地域や職場単位で続々九条の会が作られていった。04年6月からの最初の1年で約2,000の九条の会がつくられ、続く2005年6月から06年6月までの1年でさらに3,000の九条の会がつくられた。06年から07年6月までに約1,000、07年6月から08年6月までに約1,000という増えようである。ついに、08年4月には会は7,000を超えた。
こうした九条の会の発展と並行して、憲法改悪反対共同センターや労働組合、市民団体による改憲反対の行動も活発化した。こうした憲法運動の昂揚と、逆のカーブをとって、改憲に賛成の世論は減り続けた。読売新聞の調査では、改憲の本格化した2004年4月には改憲賛成が65%に達し、反対はわずか22.1%まで減っていた。ところが九条の会の運動が盛り上がるにつれ、改憲賛成の世論は減り続けた。05年には、賛成は60.6%に、06年には55.5%に、07年には46.2%と50%を割り込み、ついに、08年の4月には、賛成42.5%に対し反対は43%と改憲賛成派は反対派を下回ってしまったのである。
九条の会を筆頭とした改憲反対の運動が、改憲をめぐる世論に影響を与えたことは明らかであった。
改憲への国民的合意形成の軽視
改憲強行路線の挫折をもたらした第2の要因は、こうした改憲反対の声と言説の活発化を安倍政権が過小評価し、国民の改憲への合意形成を軽視したことである。安倍首相自身は確かに、政治家になって以来一貫して、改憲に執念を燃やし、改憲の必要性を訴え続けていたからこの期に及んで、改憲の必要性など改めて訴えるまでもないものと思われたかもしれない。とくに、90年代末からの北朝鮮のミサイル実験、拉致問題の暴露、さらに核実験は、北朝鮮脅威論を盛り上がらせ、9条の改正をしないで日本の安全は守れるのかという、不安を増大させていた。安倍政権として、そうした改憲に有利な条件に乗って一気に改憲に持ち込めるという判断であったと思われる。
安倍氏自身の改憲論は、政治家になって以降、ほとんど変化のない、陳腐化したものにとどまっていた。安倍氏は改憲の必要性として3つの理由をあげていたが、その第1は常に「押しつけ憲法論」であった。例えばこうである。「現行憲法を『不磨の大典』のごとく祀り上げて指一本触れてはいけないというのは一種のマインドコントロールだと思います。私は三つの理由から憲法を改正すべきと考えています。一つ目は現行憲法はニューディーラーと呼ばれた左翼傾向の強いGHQ内部の軍人たちが――しかも憲法には素人だった――短期間で書き上げ、それを日本に押し付けたものであること。国家の基本法である以上、やはりその制定過程にはこだわらざるをえません。」
しかし、この「押しつけ憲法」論については、その事実に関していくつもの反論が出されているだけでなく、制定以来60年以上たって、国民が何度も憲法を「選びなおし」ている現在では、自民党の改憲派のなかからも「これでは改憲の理由としては弱い」という声の上がっている代物であった。
にもかかわらず安倍首相はこれをくり返し続けたのである。国民に新たな情勢を踏まえながら改憲の必要性を訴え、改憲に向けての国民的合意を調達する努力がおろそかであったことは明らかであった。確かに安倍政権が登場して以来、日本会議など右翼の活動は活発化していたが、改憲の必要性を訴える広範な国民運動も起こらなかった。
保守派政治家内部の亀裂
それどころか、第3に、安倍政権の改憲にかける異常とも言える意欲は逆に、保守派政治家の中から、安倍氏の意図に対する疑いを増大させ、保守支配層内でも一致して改憲に邁進するという動きを作れなかったことがあげられる。
とくに安倍政権が、「戦後レジームからの脱却」を掲げ、改憲をその一環として位置づけたことは、保守政治家の中の安倍氏に対する疑いを深めた。なぜなら、安倍氏が「脱却」を謳う「戦後レジーム」とは、戦後保守政治がつくってきた体制そのものであったからだ。安倍氏が打倒の対象とする「戦後レジーム」とは、憲法には手を触れずに自衛隊はもつがそれを海外に派兵したり軍事大国になることを否定する「小国主義」の政治、西側とも東側とも外交を通ずる「全方位外交」、経済成長優先の政治、などを指した。こうした戦後体制は、冷戦終焉後の軍事大国化、構造改革の政治によってその再編が迫られてきたが、それでもそれらはなお、多くの保守政治家の原点でもあった。安倍政権はそこに手をつけたのである。
こうした「戦後レジームからの脱却」論に対して、早くは後藤田正晴や宮沢喜一らが異を唱えていたが、野中広務やさらに現役の保守政治家の中からも異論が唱えられるようになった。彼らの多くは安保条約や自衛隊には賛成であり、その延長上に、自衛隊の海外派遣による「国際貢献」にも賛成であった。それにもかかわらず、彼らの多くは、中国への侵略戦争、太平洋戦争とそれを引き起こした戦前の政治体制への復帰には反対であった。安倍政権の唱える「戦後レジームからの脱却」なるものがそれをとりまく中堅、若手政治家らの右翼的雰囲気と相俟って、戦前的な体制をめざしているのではないかという点に、保守政治家たちの一部が強い懸念を抱いたのである。
それを言説にしたのが、保守派知識人であった。安倍政権到来後から、相次いで立花隆や保阪正康ら保守派の言論人が、安倍の改憲論に反対して声をあげた。これら言説は、『現代』のような大衆雑誌に掲載されたからその影響も小さくなかった。
民主党の離反
最後の直接的な要因は民主党の離反である。もともと、自民党は、改憲実現のためには民主党を抱き込むことが不可欠の条件であることを見越して早くから民主党との協調に努めてきた。とくに、2000年に発足した国会の憲法調査会では、民主党との協調が意識的に進められた。こうした協調戦略のかいあって、とりわけ衆議院の憲法調査会の報告書では民主党の意見もとり入れた改憲での合意点が前面に出たものとなった。
協調の動きは先に触れた改憲手続法の制定協議に続いた。ここでも、自民、公明側の与党と民主党の間では緊密な協議が行われたのである。ところが安倍政権の強行路線は、こうした自民党と民主党との協調関係にヒビを入れたのである。
しかも、亀裂は、別の、より深刻な理由からも深くなった。改憲反対の声の高まりが民主党議員や候補に強い影響を与えないわけにはいかなかったことである。さらに安倍首相の改憲言説、とくに「戦後レジームからの脱却」論は民主党にも動揺を与えた。自民党が改憲タカ派の路線を強くうちだすにつれ、広範な大都市市民層を支持基盤に抱える民主党としては自民党政権の改憲路線にそう易々とついて行ける状況ではなくなったのである。小沢代表の改憲手続法での反対論は、参院選前の政局をにらんだ言説にすぎなかったが、それと並行して、「安倍政権のうちだす改憲路線には反対だ」という民主党議員も増えてきたのである。しかも、小沢の反自民対決路線の下で、民主党内の護憲派も発言の自由をうる機会が多くなった。こうした事態も民主党の改憲離れに拍車をかけたのである。
07参院選での民主党の躍進は、民主党の改憲離れにさらに拍車をかけた。安倍批判の声のなかに、安倍が推進した改憲タカ派路線に対する反発や懸念があったことを議員たちは肌で感じていた。新議員たちを中心に、自民党の改憲に距離をおこうという気分が、民主党内で増大したのである。こうして民主党の改憲離れは、たんに政局的なものから一歩「前進」した。
2 福田政権による改憲戦略の建て直しはいかなるものか?
(1)改憲状況の一層の困難
こうした改憲強行路線の破綻の後を継いだのが福田政権であった。
明文改憲の困難さの増大
福田政権下では、明文改憲をめぐる困難は一層深刻さを増した。まず改憲強行路線を破綻に追いやった「九条の会」をはじめとする改憲反対運動は勢いを持続し、先にひと言ふれたように、改憲反対の声の増加は、安倍政権後も止んでいなかった。読売新聞における改憲賛成と反対の声の逆転は、今年の4月の調査結果であることがそれを象徴していた。
民主党の躍進によって参院において与野党逆転が生まれたため、民主党の対決路線は一層活気を増し、それも相俟って、民主党の改憲への消極性は選挙後も続いた。改憲手続法で設置が義務づけられた憲法審査会も開店することができないままであった。
最大の困難は、参院選でも現われた構造改革への怒りが、後期高齢者医療制度、「名ばかり店長」「日雇い派遣」など非正規労働者の待遇や貧困問題で噴出したため、政府が「改憲どころではない」状況に追い込まれたことであった。
改憲圧力と苛立ちの増大
しかし他方、改憲を求める内外の圧力、とりわけブッシュ政権の圧力は一向に収まる気配がないどころか、安倍政権のあっけない挫折で、一層苛立ちを増していた。
おまけにブッシュ政権の神経を逆なでさせるような事態が起こった。参院での与野党逆転の事態が、今まで歴代政権が積み重ねてきた自衛隊の米軍支援に待ったをかける状況を生んだからである。民主党は07参院選における党の公約で、テロ対策特措法の延長反対、自衛隊のイラクからの撤兵を掲げていた。テロ対策特措法は、07年11月で期限切れを迎えるので、安倍政権、福田政権は何とか民主党の同意を得て、テロ対策特措法の延長を決めようと画策したが、衆院選近しと考えた小沢指導部はこれを一蹴したため、テロ対策特措法の期限が到来し、護衛艦の撤収を余儀なくされたのである。解釈改憲すら後退の危機に瀕した。
こうした事情から、福田政権は、明文改憲の建て直しのみならず、解釈改憲の後退にも歯止めをかけ、とにかくブッシュ政権の苛立ちを静めることを求められたのである。
こうした2つの相反する事情、すなわち改憲をめぐる困難とアメリカの圧力の増大を前にして、福田政権は、改憲戦略の見直しを迫られた。福田政権の新戦略は3つの柱からなっていた。
(2)民主党との協調体制の再建
福田政権の改憲新戦略の第1は、安倍政権の改憲強行路線で破綻した民主党との協調体制の再建であった。
大連立構想の思惑
改憲を実行するには、民主党を抱き込まねばならないことは自明であったが、安倍政権は小沢体制の短命を予想して強行路線にでた結果、民主党との長年の協調体制にひび割れを生じさせてしまった。おまけに、国民の改憲に対する警戒心は民主党の消極性を強めている。これを回復しなければ、明文改憲の再出発はできない。それだけではない。参院の与野党逆転状況をふまえれば民主党との協調体制を再建しなければ、自衛隊の海外派兵にも支障が出ることが明らかとなった。かくて、協調体制再建は福田政権の戦略の第1課題となった。
07年10月末に突如浮上した福田―小沢間の「大連立」構想は、こうした福田政権の戦略からいえば、必然であった。大連立ができれば、改憲問題は、解釈改憲の前進も含めて一気に片が付くからである。大連立構想は、小沢代表の民主党内での孤立であっけなく崩壊したが、今後も根強く再燃する構想であることは、これが民主党との協調体制の切り札であることから必然である。
新憲法制定議員同盟への民主党幹部の就任
他にも福田政権側からの民主党との協調体制再建の手が打たれている。08年3月4日に総会を開いた新憲法制定議員同盟の新戦略にそれが現われている。同会では、新役員のなかに、民主党の現職幹部を取り込んだのである。一人は、民主党幹事長の鳩山由紀夫の顧問への就任であり、もうひとつが、副代表の前原誠司の副会長への就任である。これは自民側からのみならず民主党側からも「画期的」な出来事であった。改憲実行組織の幹部に、自民党と民主党幹部が顔をそろえたからである。
しかし民主党との協調体制の焦点は、海外派兵恒久法制定をめぐっての民主党との協調体制づくりに置かれた。この点は改めてふれる。
(3)改憲国民運動の再建と護憲運動に対する抑圧
福田政権の新戦略の第2は、改憲国民運動の再建戦略である。これも安倍政権の改憲強行失敗の教訓を踏まえた戦略である。安倍政権が改憲についての国民的合意形成をおろそかにし、「九条の会」などが国民に訴えるのを放置したことへの反省である。
改憲国民運動を
先にふれた新憲法制定議員同盟総会は、この点でも新方針をうちだした。九条の会に匹敵する改憲国民運動の再建であり、その具体化として、全国の都道府県に新憲法制定議員同盟の地方支部を設置するという方針である。
改憲派は改めて九条の会の運動を重視し、遅ればせながら、改憲国民運動の強化をはかろうというのである。日本青年会議所で、全国で改憲派と護憲派の討論を組織し、改めて改憲論の浸透をはかろうという試みが進んでいるのもこの一環である。
憲法運動への規制と干渉の強化
しかし、こうした国民運動が当面さほど盛り上がらないことは、改憲派にとってもある程度予測済みのことだ。そこで一層重視しているのが、九条の会をはじめとして、全国で盛り上がる改憲反対運動に対する規制である。
その点で、近年強まっているビラ配りへの規制、映画「靖国」上映に対する干渉、さらに、九条の会への干渉が注目される。とくに、市民のビラ配布活動に対する規制が近年強まっている。
はじまりは2004年2月の立川自衛隊官舎への「自衛官のイラク派兵反対」を訴えるビラ配布を理由に「立川テント村」の活動家3人が住居侵入で逮捕・起訴された事件であったが、続いて、3月には共産党のビラ配布を行っていた国家公務員が、国家公務員法102条の政治活動禁止違反で訴追された事件が起こった。続いて2005年9月にも、国家公務員のビラ配布に対する弾圧が起こり、その間2004年12月には、今度は共産党のビラを配布した市民が逮捕され住居侵入で起訴される事件も起こった。
これら一連の事件には、注目すべき共通点がある。第1に、これら事件はいずれもビラの配布に焦点を合わせ、これを弾圧しようとしている点である。第2は、取り締まりの対象が共産党か、立川テント村のように長年市民運動を継続している組織をねらったものであること、つまり組織の運動をねらったものである点である。第3は、これら逮捕・起訴がいずれも組織的、計画的であること。第4は弾圧のたびに取り締まり対象が拡大している点である。すなわち取り締まりは、まず国家公務員から市民へと拡大し、また、ビラ配布でもマンションの各戸のポストへの配付に対する取り締まりから集合ポストへの配布にまで拡大しているなどである。
改憲反対運動を抑止しようというねらい
こうした特徴を見ると、これら一連の弾圧事件が、この間の改憲や構造改革に対する政党や市民の運動の活発化に冷水を浴びせようという意図の下に行われているのは明らかである。行論に関して注目すべきは、これが、新憲法制定議員同盟の掲げる九条の会運動への対抗、九条の会への規制というねらいに収斂しつつある点である。
しかも、こうしたビラ配布活動への弾圧に加えて、最近では、日教組の教研集会へのプリンスホテルの会場使用拒否や、映画「靖国」への文化庁からの助成に対する自民党議員のクレームと上映の自粛問題が起こっている。ここで見逃すことができないのは、「靖国」への助成に対し自民党有村議員らは国会での質問で、助成の審査に当たる「日本芸術文化振興会」の専門委員のなかに「映画人九条の会」のメンバーがいることを問題にしたことである。これは、干渉の対象が九条の会に絞られつつあることを象徴している。さらに近年藤沢市議会では、議員が、藤沢市内「六会ふるさとまつり」に「むつあい九条の会」が出店したことに対し、「政治的な団体の公的施設利用は問題だ」というかたちで干渉を行おうとした事件が起こった。
これら一連の干渉事件は、改憲反対の運動規制との関係では二重のねらいを持っている。これら弾圧・干渉は、一方では、改憲反対運動の担い手としての教員や公務員、さらに共産党のような組織にねらいを定め、彼らの活動を抑え込もうというねらいを持っている。他方、これら事件には、ビラの配布や会場の使用という九条の会をはじめとした市民の運動のもっとも基本的な活動の手段を規制することによって改憲反対運動を規制しようというねらいもあるのである。
こうして福田政権下の新戦略の下で、改憲反対の市民運動に対する攻撃が強まっているのである。
さて、福田政権の新戦略の第3は、海外派兵恒久法の制定を通じて解釈改憲を先行させようという戦略だが、これについては節を改めて検討しよう。
3 なぜ、海外派兵恒久法が改憲の焦点として浮上したのか?
(1)海外派兵恒久法の2つのねらい
海外派兵恒久法が福田政権当面の解釈改憲戦略の焦点として浮上しているのにはそれなりの理由がある。改憲戦略との関係では海外派兵恒久法は、2つのねらいを持っている。
アメリカの苛立ちの解消-特措法の2つの限界突破
ひとつのねらいは、明文改憲が実現する前にも、自衛隊派兵を拡大して、先述したように増大するアメリカの苛立ちを抑えるねらいである。この点では、08年7月6日からのサミットでの日米首脳会談時に、ブッシュ大統領が、福田首相に対し、アフガンでの自衛隊の活動の拡大を促しているようにアメリカの圧力は増すばかりである。
では、恒久法で政府は自衛隊派兵をいかに拡大しようとしているのであろうか。
現在の米軍活動に対する後方支援については2つの限界があるが、海外派兵恒久法で政府はこれら2つの限界の突破をはかろうとしているのである。限界のひとつは、現在の後方支援のやり方は、恒久法がないため、米軍が軍事作戦を開始してから、特措法形式で対処するので、米軍の軍事作戦への支援がどうしても遅れるという難点である。また、特措法という時限立法形式であるため、米軍の作戦行動の長期化にともない、いちいち期間を延長しなければならず、場合によっては、テロ対策特措法のように延長に失敗する危険もある点である。
もう一つの限界は、これまでの特措法形式の支援では、米軍支援の中味が限定されてアメリカの要請に十分に応じられていない点である。例えば、イラク派兵軍では、警護活動や治安活動ができない点が大きい。
これら2つの限界を打破するためには、明文改憲が一番であることは間違いないが、海外派兵恒久法の制定により、米軍が出動してからいちいち立法化しないで自衛隊を派兵できるようにすることは、第1の限界突破に大きな役割を果す。また海外派兵恒久法制定に際して、後方支援内容を拡大することで、第2の限界にも対応しようというのである。
民主党を改憲協議に巻き込む梃子
しかし改憲にとっては、海外派兵恒久法のもう一つのねらいがさらに重要である。それは、この海外派兵恒久法を梃子に民主党との協議を再開するというねらいである。
では一体なぜ海外派兵恒久法が民主党との協調再開の梃子となるのであろうか。それは、この点について民主党の側から度重なるメッセージがでているからである。
最初のメッセージは、『世界』2007年11月号に載った小沢一郎代表の個人論文というかたちで発せられた。小沢氏はここで、アメリカ追随の自衛隊の派兵は憲法9条に違反すると述べたあと、国連の決議に基づく自衛隊の派兵であればたとえ武力行使を含むものであっても9条には違反しないと述べ、ISAF(国際治安支援部隊)への参加の意思を表明したのである。福田政権は、このメッセージに飛びついた。小沢論文は、「国連という名目さえはっきりすれば、自衛隊の海外派兵に応ずる」というメッセージと読んだのである。その直後の福田―小沢会談での大連立の合意点にこの点が入っていたことはそれを示していた。
この大連立構想は潰れたが、民主党は続いて自民党に対しメッセージを発した。それは、自民党が出した新テロ法案に対して民主党が07年12月末に提出した対案の中にあった。新テロ法案は、テロ対策特措法の延長が民主党など野党の反対で参院を通らなかったことに対し政府の出した提案であった。新テロ法案は、自衛隊のアフガンにおける任務を給油一本に絞り、かつ1年の期限で行おうという譲歩したものであった。民主党はこれにも反対したが、対案中に、「海外派兵恒久法の制定なら乗ってもいい」というメッセージを忍び込ませたのである。それが対案25条であった。それはこういっていた。「国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主導的に寄与することを含む我が国の安全保障の原則に関する基本的な法制の整備が速やかに行われるものと」しという具合である。
こうした経緯をみると、海外派兵恒久法は、破綻している民主党との改憲協調体制の再建の唯一と言ってもよい糸であることが分かる。
(2)海外派兵恒久法の骨格
では一体こうした二重のねらいをもって制定が画策されている海外派兵恒久法とはいかなる内容を持ったものなのであろうか?
海外派兵恒久法は、福田政権が、民主党と改憲をめぐる協調体制を再建する切り札であるから、民主党を協議の土俵に引きずり込むためには、かなりの譲歩をいとわないと思われる。そのため、その内容は自民党、民主党の今後の協議の中で大幅に変えられることが予想され、現時点で確定することは難しいが、福田政権が考えている海外派兵恒久法の中味は以下の3点を柱としている。
米軍の軍事作戦への一層迅速な派兵
政府が海外派兵恒久法に入れたいと考えている第1の点は、米軍の軍事作戦に対し一層迅速に派兵できるように、派兵の基準をできるだけ広範囲にとることである。アメリカ政府も何より、この点を望んでいる。海外派兵恒久法の原案としては、2006年8月に自民党国防部会防衛政策小委員会がつくった「国際平和協力法案」(いわゆる石破試案)がもっともまとまったものであるが、この石破案では、出動基準としては、まず国連決議、国連の要請をあげながら、同時に国連の要請がなくとも「武力紛争当事者の合意にもとづく要請」や「国際連合加盟国その他の要請」そのほか「国際の平和及び安全を維持するため我が国として国際的協調の下に活動を行うことが特に必要であると認める事態」には派兵ができるとしている。つまり、国連の要請があろうとなかろうと、いつでも派兵できるようになっているのである。
これに対して、民主党は「国連決議若しくは国連の要請にあったとき」と限定してくることは明らかなので、この間の調整が法案の成否の鍵となるであろう。
アメリカは、自衛隊の派兵を国連の要請に絞ることに強い抵抗を示しており、日本の外務省も防衛省も、それではアメリカの要請に迅速に呼応できないと考えているから、事実上、この基準をどうするかが、海外派兵恒久法の最大の焦点となろう。
後方支援活動の拡大
政府が法案内容に含めたい第2の点は、後方支援の中味を拡大し、少なくとも、その中に「安全確保活動」、「警護活動」を入れたいという点である。これさえ入れば、事実上自衛隊の武力行使は解禁になるからだ。この点では、はじめて海外派兵恒久法の検討を行った小泉政権下の「国際平和協力懇談会」の報告書が注目すべき案を提示していた。(ちなみに同懇談会は福田現首相が官房長官として取り仕切ったものである点が興味深い。)それは、後方支援の活動を、いちいち列記するのでなく、逆にネガティブリスト方式にして、禁止される活動を列挙し、あとは解禁するという方式である。
それに対して石破試案は、後方支援活動に「安全確保活動」「警護活動」を加える方式をとっていた。どちらになるかは分からないが、民主党は、これまでの小沢発言から推測すると、第1の「国連原則」で妥協が成り立てば、この点は容易に合意されると思われる。
武器使用の拡大
第3は、自衛隊の武器使用の拡大を入れることである。この点も第2と並んで現地の自衛隊の望んでいるものであるが、「国際平和協力懇談会」報告も、石破試案もこの点は明記している。また、民主党もここはすんなり行く可能性がある。
結局、もっとも中心的争点は、第1の自衛隊派兵の基準をどう書くかである。この合意次第では、自衛隊の派兵は、事実上限界がなくなる危険が出てくる。福田政権が海外派兵恒久法で民主党を巻き込むことに成功するようなことがあれば、改憲が容易ならぬ段階に入ることは明らかである。
小括 改憲を阻むために何が必要か?
以上のような改憲をめぐる新たな情勢に立って、改憲を阻止するにはいかなる活動が望まれるかを最後に手短に指摘しておきたい。
(1)海外派兵恒久法制定阻止に全力を
改憲を阻止し、改憲策動の息の根を止めるためにまず必要なことは、今、福田政権が改憲の焦点として提出をもくろんでいる海外派兵恒久法の制定阻止のために全力を挙げることである。
海外派兵恒久法阻止に有利な条件
運動次第では海外派兵恒久法の制定を阻止できる有利な条件がある。まず第1に、政府側には時間が限られていることである。新テロ対策特措法は先述のように1年の期限付きであるため、09年1月には切れてしまう。ここでまた自衛隊をインド洋海域から撤退させるという「愚」だけは政府は何としても避けたい。しかしそうするためには、この秋の臨時国会が勝負である。そこで、私たちの頑張り次第では、法案を潰すことは可能である。
有利な点の第2は、新テロ対策特措法延長にせよ、海外派兵恒久法にせよ、後期高齢者医療制度をはじめ、国会で与野党が激突している状況下では、民主党が自民党との協議に乗ることは極めて難しいという点である。
そこで、今福田政権は、事態乗り切りに3つのケースを想定している。第1のケースは、民主党との協議がうまく成立して海外派兵恒久法が制定されることである。しかしこの展望は現在極めて薄い。衆院選を前に民主党は一層自民党の誘いに乗りにくくなっているからだ。そこで2番目の可能性として急浮上しているのが、新テロ対策特措法を民主党の主張であるISAF参加を含めて修正し民主党を抱き込む方式である。しかし、こちらは、防衛省などが現地の危険を理由に難色を示しているほか、公明党も難色を示している。公明党としても、自民党と民主党の協調体制ができてしまうことは痛しかゆしだから、なかなか短期にはまとまらない。
そこで出てくる第3のケースは、新テロ対策特措法の延長である。これでは、しかし民主党は07年臨時国会で反対した手前、絶対に乗れない。そこでこの案の場合にはふたたび衆院で3分の2の多数で再可決という方式をとらざるを得なくなる。この第3のケースをとる場合には、それまで福田政権は解散はできないことになる。しかも、この第3案はいずれにせよ先延ばしなので、いずれ、第1案、第2案で決着をつける方向が浮上するであろう。
こうした情勢の下で、私たちは臨時国会から衆院選後をも見越して本格的な海外派兵恒久法反対の運動を組んで行く必要がある。これを粉砕することができれば、私たちは改憲を阻む現実的な展望を切りひらくことができる。逆に海外派兵恒久法を通すようなことがあれば、解釈改憲で9条に大きく穴を開けるだけでなく、明文改憲への建て直しを許すことになる。文字通りの正念場がやって来る。
(2)改憲阻止運動のさらなるバージョンアップを
改憲阻止のための課題の第2は、安倍の改憲強行路線が挫折した今こそ、九条の会を先頭につくってきた改憲を阻む運動をもう一回り大きくすることである。
そのための課題は少なくないが、ここで改めて強調しておきたいのは、憲法改悪反対共同センターなど労働組合運動の役割である。個人的な意見になるが、2つの点を強調しておきたい。
憲法改悪反対共同センターと九条の会の固有の役割
その第1は、共同センターなどの運動体と九条の会のそれぞれの役割をはっきり自覚して運動を進めることが改めて重要であるという点である。本誌の読者である労働組合員の中には、共同センターに入って活動すると同時に、九条の会にも参加して活動している人も少なくないと思われる。しかしこれら2つの組織や運動は大きく異なる特色を持っている。
九条の会は、9条の改悪に反対するというひとつの点で市民個人が集っている組織であり、共同センターのような運動体とは大きく異なる。例えば、海外派兵恒久法にしても、同じく強い関心を持つにしても、九条の会と共同センターでは、取り組む視点も取り組み方も小さくない違いと個性がある。共同センターは、海外派兵恒久法などに対して機敏に訴え、立ち上がることが必要であるが、九条の会が、そうした生起する解釈改憲や政治の動きに急いで対処しようとするとどうしても狭くなり、無理が出てくる。海外派兵恒久法の問題では、九条の会は様々な視点から、大いに学習し、議論する場を設ける必要があると考えられる。
九条の会の新しい特徴を伸ばすかかわり方を
もうひとつは、労働組合員が、「九条の会」の運動に参加していくに際して、改めて九条の会の組織の持っている新しい特徴を知り、それを伸ばすような形でかかわっていくことが大切ではないかという点である。九条の会は9人のよびかけ人による呼びかけからつくられ、今や全国に7,000を上回ってつくられているが、これらの多くは、よびかけ人、賛同人、参加者問わず、団体でなく個人が参加するというかたちでつくられ、発展している。1960年の安保改定反対運動の昂揚の基礎となった「安保改定阻止国民会議」や地域の共闘組織が社会党、共産党、総評などの団体が加盟し運営されたのとは大きく異なる恰好をもって発展している。労働組合員も政党やいろいろな団体に入っている市民も、9条改悪に反対するという点で、個人の資格で参加し様々な活動を展開している。もちろん、そのメンバーの多くは、組合員であったりあるいは政党の活動家であったりもしよう。しかし、そうでない市民も多数参加しているのが九条の会だ。それらの人々が平等に参加し会の運営にも携わっているところに、九条の会の力の源泉もある。労働組合の活動家の人々も、こうした九条の会の新しい、幅の広いつながりを一層強めるかたちで九条の会にかかわっていくことが望まれる。具体的には、九条の会をタテとヨコに拡大することに努力することである。タテとは、50歳代以上の人が多い九条の会を若い層に広げていくことであり、ヨコにとは良心的な保守支持の人にまで輪を広げていくことである。 九条の会も、共同センターをはじめとする運動組織も、改憲反対運動のクルマの両輪であり、その2つが相互に個性を発揮したとき運動はさらに発展をみる。九条の会のこうした新しい性格をもっと伸ばすことが、改憲強行路線が一頓挫を来たし新たな攻撃に入ろうとしている現在、私たちがめざすべき、運動の一層の拡大の焦点のひとつであると確信している。
わたなべ おさむ 1947年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科教授。専門は政治学、憲法、日本近代政治史。著書:『憲法改正は何をめざすか』(岩波ブックレット2001年)、『憲法「改正」―軍事大国化・構造改革から改憲へ』(旬報社2005年/増補版2005年) 、『構造改革政治の時代―小泉政権論』(花伝社2005年) 、『安倍政権論―新自由主義から新保守主義へ』(旬報社2007年)、共編著:『講座 戦争と現代1「新しい戦争」の時代と日本』(大月書店2003年)、『講座 戦争と現代5平和秩序形成の課題』(大月書店2004年)、『対論!戦争、軍隊、この国の行方―九条改憲・国民投票を考える』(今井一編 青木書店2004年)、監修:『新自由主義』(作品社2007年)他多数
この論稿は、全労連の月刊「全労連」(9月号No140号)に掲載された論文を渡辺治氏と全労連の了解のもとに掲載します。